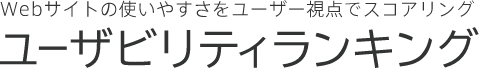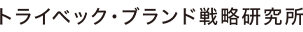まず、改めて事業内容を教えていただけますでしょうか。
竹下:
当社は建設業を主軸とする総合建設業として事業を展開しています。建物の建設だけでなく、不動産開発やエンジニアリング、環境エネルギーなど、事業領域を広げています。

コーポレートサイトの運用方針についてお聞かせください。
南野:
当社は BtoB事業を中心としており、コーポレートサイトでは基本的にマルチステークホルダーに向けた幅広い情報発信を目指しています。ESG・サステナビリティやIR情報など、特定のターゲット向けのコンテンツもありますが、サイト全体としては広く情報発信することを重視しています。
またBtoB企業という特性上、チャットボットなどのBtoC対応、顧客対応ツールの導入は他に比べて現状では優先度が低いと判断しています。むしろ、ユーザビリティの向上と必要な情報の適切な発信に注力していますね。
運用・改善の体制についてはどのような形で行われているのでしょうか。
南野:
コーポレートサイト担当者会議(コーポレートサイト部会)を開催し、各事業部門の担当者と情報共有や改善点の検討を行っています。我々コーポレート企画室コーポレートコミュニケーション部が事務局として全体を統括し、各部門がそれぞれのコンテンツを担当するという体制ですね。
また、年1回トライベックの診断を受け、その結果に基づいて改善を進めています。挙げられる改善項目はさまざまですので、実現の難易度とコストを考慮して優先順位をつけ、費用対効果の高いものから順次対応しています。

取り組みを通じ、ユーザビリティ向上の成果を感じる例について教えていただけますでしょうか。
南野:
ユーザビリティ診断で大きく順位が改善する1年前、2017年にサイトリニューアルを行いました。以降、継続的な改善に取り組んだことで、今回の結果に繋がったと考えています。
竹下:
最近の具体的な成果としては、2024年1月に新CMを公開した際、診断での指摘を踏まえてトップページにカルーセルを導入し動線を整備したところ、動画自体へのアクセス上昇だけでなく、関連ページへのアクセスが増加するなどの効果が見られました。
運用における課題についてはどのようにお考えでしょうか。
南野:
各事業部門からも情報発信のニーズが年々高まっており、さまざまな工夫や改善の相談が増えています。サイト全体の統一性を保ちながら、要望にどう応えていくかが課題ですね。
また、リニューアルから時間が経過していることもあり、今後どのようにサイトを進化させていくかという点も重要な検討事項です。ステークホルダーをはじめ、お客様が求める情報の粒度や形式は年々変わっていきます。新しい取り組みを行う際、今の施策が最適解なのかという課題意識も持っています。

最後に、今後の展望をお聞かせください。
南野:
ユーザビリティの向上については、常に上位にランクインできていますが、さらなる改善の余地があると考えています。特に、ブランド力向上に寄与する情報発信の強化が今後の課題です。
コーポレートコミュニケーション部としては、インナー・アウター問わずブランディングを担当しており、その中でもコーポレートサイトの重要性は高まっています。今後は、このユーザビリティの高さを少なくとも現状維持しながら、ブランド力向上につながる情報発信の方法を模索していきたいと考えています。